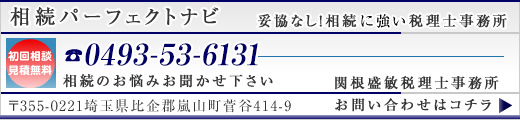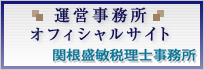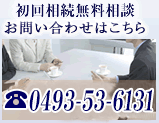相続が発生した方

- 財産目録の作成
- 遺言書の確認
- 相続放棄の手続
- 亡くなった人の確定申告書の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 名義変更

必ずしも作成する必要はありませんが、作成することで遺産を分ける話し合いをするとき便利です。

亡くなった方が遺言書を残していないかを確認します。自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認が必要となります。

原則として、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。債務などのマイナスの財産が多い場合などは検討する必要があります。

亡くなった人が生前収入があり所得税を支払う必要があった場合、原則として、相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内に亡くなった人の確定申告書を提出する必要があります。また、還付となる場合には所得税が戻ってくることになります。

財産目録を基に遺産の分け方を決めたら、遺産分割協議書を作成します。相続人全員の自筆の署名と実印を押印し、印鑑証明書を添付します。不動産登記や、金融機関での名義変更等で必要となりますので必ず作成します。

遺産分割協議書を基に不動産や預貯金、株式等の名義変更を行います。
争族対策に追加して相続税の申告の必要があります。
 1.相続税の申告
1.相続税の申告2.土地の評価
3.遺産分割
4.税務調査への備え
5.相続税を現金一括納付できない方
6.相続終了後の相続人の対策
6.次の相続対策

相続税の申告にはいくつかのポイントがあります。
- 正確な相続税額の計算
- 円満な遺産分割
- 納税資金の準備
- 税務調査までを視野に入れた財産の洗いだし
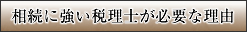 |

土地の評価は税理士によって変わります。
その結果、依頼した税理士によって相続税額に差額が出てくることもあります。
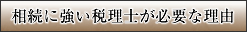 |

遺産分割のポイント
- 配偶者の税額軽減の利用
- 代償分割の利用
- 生前の贈与財産を遺産分割に含めるかどうかの検討
- 賃貸不動産の分割の検討

相続税の申告において、税務調査を受ける確率は約30%となっています。 さらにその税務調査を受けた方のうち約85%の方が申告漏れを指摘されています。 この申告漏れのうちほとんどがご家族の名義預金なのです。
 |
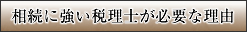 |

相続税は現金一括納付が原則です。 現金一括納付が困難な場合、納付方法の検討をします。
- 延納の検討
- 物納の検討

賃貸不動産を相続した場合には、その後不動産収入の申告の必要がありますし、 その不動産を売却した場合には譲渡所得の申告の必要があります。
これらの申告については、相続税の申告と密接な関係があります。 相続税の申告を済ませたら終わりではなく、その後のアフターフォローも大切です。
- 不動産の有効活用
- 不動産の売却
- 不動産の贈与
- 不動産の組み換え
- 信託制度の利用

一難去ってまた一難とならないよう、綿密な計画が必要です。 次の相続(二次相続)は最初の相続と関連があります。 アフターフォローがかかせません。